IDWR 2016年第48号<注目すべき感染症> 梅毒 2016年第1~47週までの疫学的特徴

注目すべき感染症、注:PDF版よりピックアップして掲載しています。
梅毒 2015年第1~53週と2016年第12週までの疫学的特徴
2016年第1週から第47週(2016年1月4日~11月27日)に診断され、梅毒として報告された症例数(2016年11月30日時点、暫定値)は4,077例であった。昨年同時期(2,328例)と比較して1.8倍であり、性別は男性2,848例、女性1,229例、昨年同時期(男性1,668例、女性660例)のそれぞれ1.7倍、1.9倍であった。
報告都道府県別では、東京都(1,524例;前年同時期924例、1.6倍)、大阪府(532例;同269例、2.0倍)、神奈川県(257例;同138例、1.9倍)、愛知県(230例;同102例、2.3倍)、埼玉県(166例;同92例、1.8倍)、兵庫県(158例;同73例、2.2倍)、千葉県(116例;同65例、1.8倍)、北海道(104例;同51例、2.0倍)、福岡県(101例;同62例、1.6倍)で多く報告された。
感染経路別では、男性においては詳細が不明等の報告660例を除いた2,198例の中で、異性間性的接触が1,480例(昨年同時期716例、2.1倍)、同性間(異性間・同性間の重複を含む)性的接触が718例(同533例、1.3倍)であった。また、女性においては詳細が不明等の報告275例を除いた960例の中で、異性間性的接触は951例(同473例、2.0倍)、同性間(異性間・同性間の重複を含む)性的接触が9例(同6例、1.5倍)であった。
病型は、感染早期の患者動向を反映し、感染性の高い早期顕症梅毒が、男性で2,113例(内訳:1期1,136例、2期977例。早期顕症梅毒の前年同時期1,152例、1.8倍)、女性で735例(内訳:1期220例、2期515例。同、前年同時期365例、2.0倍)とそれぞれ増加した。無症候は男性653例(同442例、1.5倍)、女性463例(同277例、1.7倍)、晩期顕症梅毒は男性75例(同71例、1.1倍)、女性24例(同10例、2.4倍)が報告された。先天梅毒は14例(同11例、1.3倍)が報告された。
年齢分布として、男性は20~54歳の各年齢群より報告されており(2,377例:男性報告数全体の83%)、5歳ごとの年齢群で最も割合の高い群は40~44歳(445例:男性報告数全体の16%)であった。女性は15~39歳の年齢群が女性報告数全体に占める割合が約8割(960例)であり、20~24歳(387例:女性報告数全体の31%)が最も割合の高い年齢群であった。
15歳以降5歳ごとの年齢群(15~19歳から55~59歳まで)の分布は、以下であった。
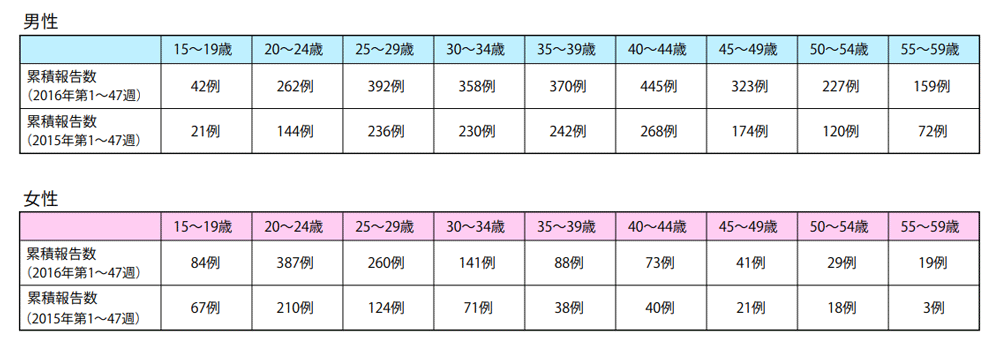
2010年以降梅毒の報告数は増加傾向に転じており1、報告数は依然として多い状態が継続している。全国的に増加がみられており、東京都や大阪府等の大都市と、その周辺の地域からの報告が特に多い。昨年に引き続き、男女の異性間性的接触による報告数増加の傾向が続いており2、母子伝播による先天梅毒も引き続き報告されている。今後の梅毒の発生動向に引き続き注意しながら、特にリスクが高い集団に対する啓発活動が重要である3。具体的には、不特定多数の人との性的接触はリスク因子であり、その際にコンドームを適切に使用しないことがリスクを高めること、オーラルセックスやアナルセックスでも感染すること、梅毒は終生免疫を得られず再感染することなどが啓発のポイントとして挙げられる3,4。
早期発見、早期検査が重要である3。感染が疑われる症状がみられた場合には、早期に医師の診断・治療を受けることが重要である。医師が梅毒と診断した場合には、感染症法に基づく届出を行う必要がある。梅毒に感染していたことがわかった場合は、周囲で感染の可能性がある方(パートナー等)と一緒に検査を行い、必要に応じて、一緒に治療を行うことが重要である。梅毒の感染経路、症状、治療、予防等に関しては、「梅毒に関するQ&A」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/qanda2.html)を参照されたい。
参考文献
- IASR 梅毒2008~2014年
- 感染症発生動向調査週報(IDWR)「梅毒2015年第1~53週と2016年第12週までの疫学的特徴」
http://www0.nih.go.jp/niid/idsc/idwr/IDWR2016/idwr2016-12.pdf - 性感染症
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/seikansenshou/index.html - 性感染症に関する特定感染症予防指針の改正(概要)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/seikansenshou/dl/shishin-gaiyou.pdf
国立感染症研究所 感染症疫学センター

